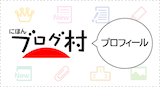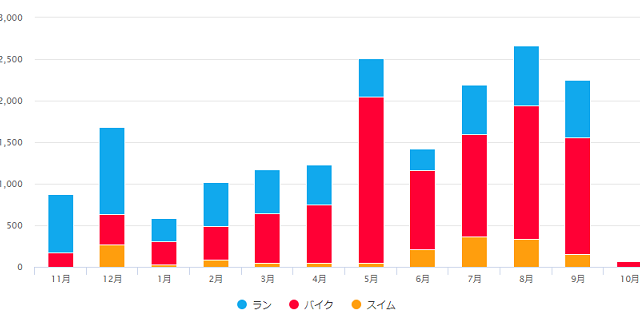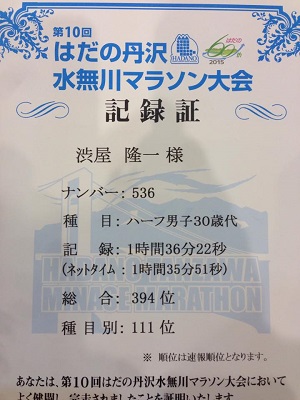日々のトレーニングには、必ず何らかの目的があります。
それを曖昧にしたままだと、当然のことながらトレーニング効果も得られにくいです。
では、どんな指標を見て、トレーニングすれば良いのでしょうか?
素人なりにまとめてみました。
<スポンサードリンク>
バイク:パワートレーニングの土台となる理論
主にバイクで見る「パワー」について。
パワーゾーンの定義と、各ゾーンで得られる効果については、こちらの記事にまとめました。
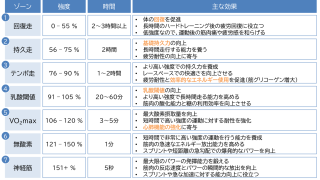
1時間維持できる最大パワーが FTP。
その FTP を基準にして、各ゾーンの強度が決まっています。
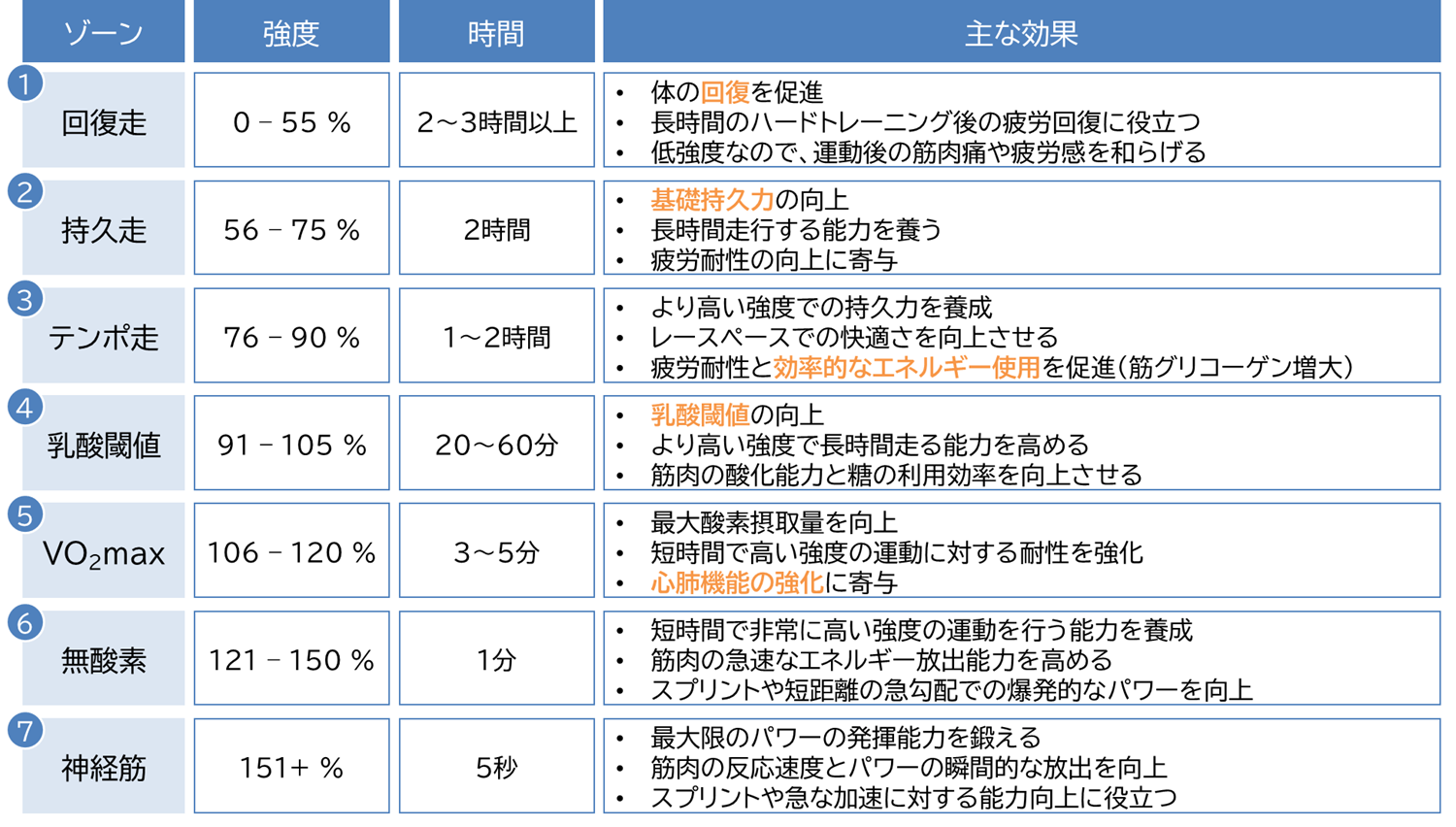 (図はコーガンの 7ゾーンモデルを使って説明)
(図はコーガンの 7ゾーンモデルを使って説明)
ラン:ペースをもとにトレーニング
ランでも同じような理論があります。
最も有名なのは、ダニエルズの理論。
ざっくり、こんな感じです。
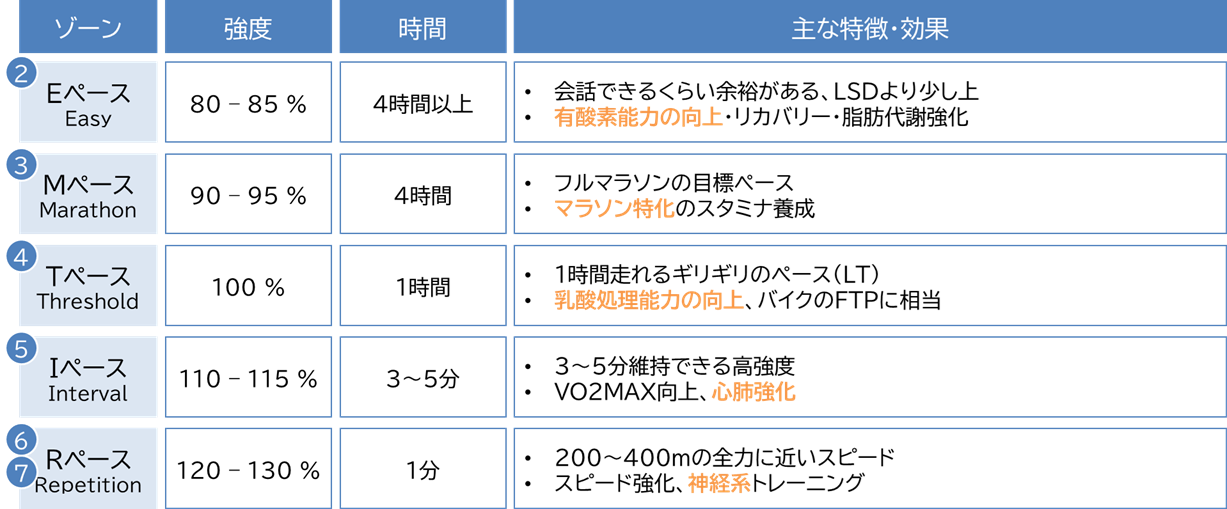
基準になるのは、1時間維持できるギリギリのペース(乳酸閾値ペース:LT)。
それをもとに強度をパーセンテージで定義しています。
ご自身のLTペースさえ分かれば、各ゾーンのペースは、こちらのサイトで計算できます。
ダニエルズ式の「VDOT計算機」
なお、各ゾーンの左側にある丸数字は、該当するバイクのパワーゾーンです。
バイクでいうパワーゾーン1(回復走)がないので、ランの方がきつく感じますね。
ちなみに私は、トレーニングの95%以上は、Eペースです。
ロングを中心に目標を立てているからですが、Mペースですら、結構キツイですよね。
マラソンシーズンに入ると、Tペースでの 2km走を 3セットなど、やったりしています。
そして、Tペース以上をやるときは、基本的にトレッドミルです。
外だと信号や起伏があったり、この時期は暑すぎて無理なので。

心拍とパワー・ペースの使い分け
ここまで、心拍数に触れてきませんでしたが。
身体にかかっている負荷を見るのに、心拍数は欠かせません。
結論から言うと、
- 低強度・長時間のトレーニングは心拍数を見る
- 高強度・短時間のトレーニングはパワー(バイク)・ペース(ラン)を見る
のがベストだと考えています。

低強度・長時間トレーニングの目的は、回復・持久力向上です。
ですから、心拍数が高くなってしまったら意味がありません。
パワーやペースを抑えますが(例:Eペース)、それでも心拍が上がってきたら、もっと下げます。
一方、高強度・短時間トレーニングの目的は、乳酸閾値や心肺機能強化です。
そのパワー・ペースを出すことに意味があるので、そちらを優先します。
ロングのトライアスロンの場合、そういう意味では心拍数を見ておけば、大きくは外さないように思います。
ショート(スタンダード・ディスタンス、オリンピック・ディスタンス)では、パワーやペースの方をしっかりチェックしますね。
なお、最近では深部体温を指標とする動きもあります。
私はパラメータが多くなりすぎると混乱するので、今は利用していません。
低強度トレーニングの日に、エアコンを入れない(室内バイク)・外を走りに行く(夏場)を意識している程度です。
お読み頂きありがとうございました。
最近は、色々と指標が多くて悩むよね~とポチっと応援お願いします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
SNSはこちらです。
Instagram:@shibuya_triathlon
Facebookページ:こちら
Twitter:@giraffe_duck